2018年12月に小人数型のサッカー指導をしている
23歳の若き指導者、エボルテサッカースクールのコーチ兼代表である
辻本拳也さんに取材をしてきました。
その時のインタビューを記事にして掲載しております。
子供に楽しんでもらうのが理想だけど指導者が勝利至上主義に走ることも少なくない
[speech_bubble type=”drop” subtype=”L1″ icon=”naoki.jpg” name=”NA”] Naoki(以下NA):今日もエボルテサッカースクールの代表である辻本さんにお話をお伺いしたいと思います。では辻本さんよろしくお願いいたします。[/speech_bubble]
[speech_bubble type=”drop” subtype=”R1″ icon=”tsuji.jpg” name=”TSUJI”]
Tsujimoto(以下TSUJI):よろしくお願いいたします。
[/speech_bubble]
[speech_bubble type=”drop” subtype=”L1″ icon=”naoki.jpg” name=”NA”] NA:今日は「子供への間違ったサッカー育成」というテーマでやっていきます。[/speech_bubble]
[speech_bubble type=”drop” subtype=”R1″ icon=”tsuji.jpg” name=”TSUJI”]
TSUJI:はい、これは少年サッカーで勝利主義をかかげて指導をすることですね。
勝ちたいがために10番の選手にボールを集めろとか
野球で言うとバントしろみたいな細かい指示をだす人は子供を指導しちゃいけないなと。
まずは子どもたちには楽しんでもらうその上でうまくなってもらうのが理想ですから。
[/speech_bubble]
[speech_bubble type=”drop” subtype=”L1″ icon=”naoki.jpg” name=”NA”] NA:それだと楽しくなさそうですね。結果にこだわっているみたいで。[/speech_bubble]
中盤省略のサッカーをしてきた子たちは川崎フロンターレのような特殊なチームに入団した時に適応できなくなるかも?
[speech_bubble type=”drop” subtype=”R1″ icon=”tsuji.jpg” name=”TSUJI”]
TSUJI:その通りです。簡単な話
小学生年代でも勝ちにこだわれば前と後ろに足の速い子とフィジカル強い子をおいて
中盤省略みたいなサッカーでも勝つことはできる
でもこのようなサッカーをしていても先につながらない
中盤省略サッカーで育ってきた子がフロンターレみたいな
特殊なサッカーをするチームに入ったら適応できなくなります。
勝ちにこだわるのではなく、どんな環境にいてもサッカーを楽しめるように育ててほしいと思います。
その上で戦術を教えていろんなサッカーに適応できるようにしてほしいですね
[/speech_bubble]
[speech_bubble type=”drop” subtype=”L1″ icon=”naoki.jpg” name=”NA”] NA:たしかにフロンターレには個人技に優れた選手がたくさんいますね[/speech_bubble]
[speech_bubble type=”drop” subtype=”R1″ icon=”tsuji.jpg” name=”TSUJI”]
TSUJI:そうですね、フロンターレの選手のようなスペシャリストを育てるってのも大事です。
いろんなサッカーに適応できなくてもこれなら別に活躍の場がある、
うまくバランスをとりながらやっていくことですね
[/speech_bubble]
ジュニア世代にもリーグ戦の導入を。Jリーグのルヴァンカップや天皇杯のベストメンバー規定は必要か
[speech_bubble type=”drop” subtype=”L1″ icon=”naoki.jpg” name=”NA”] NA:子供の頃からもポリバレントっていうのは決まってくるんですか?[/speech_bubble]
[speech_bubble type=”drop” subtype=”R1″ icon=”tsuji.jpg” name=”TSUJI”]
TSUJI:子供のうちはプレースタイルってけっこう変わったり、
ポジションコンバートして成功したりが頻繁にあるので、
極端な話、キーパーからフォワードまで全ポジションで
プレーさせて適正がなんなのかを時間をかけて見極めてあげればいいと思います。
[/speech_bubble]
[speech_bubble type=”drop” subtype=”L1″ icon=”naoki.jpg” name=”NA”] NA:現状これができている指導者がいないってことですね?[/speech_bubble]
[speech_bubble type=”drop” subtype=”R1″ icon=”tsuji.jpg” name=”TSUJI”]
TSUJI:いたとしてもあまりフォーカスされてないです。
親御さんとかも大きな大会で子供のチームが勝てば嬉しいし
周りにも自慢できますからね。
親御さんの存在が指導者を勝利至上主義に導いてしまっているのはあるかなと思います。
年間通して子供たちが試合を経験できることの方が大事なんですけどね。
リーグ戦ではなくトーナメントの試合方式だから上手い選手を出して
なんとしても勝つという意識になってしまう。
試合に出場できない子を減らすためにもリーグ戦をもっと増やすべきじゃないかなと思いますね。
[/speech_bubble]
[speech_bubble type=”drop” subtype=”L1″ icon=”naoki.jpg” name=”NA”] NA:リーグ戦というのはいい案ですよね、クラブの数も多いのだったら盛り上がりそうな気がする[/speech_bubble]
[speech_bubble type=”drop” subtype=”R1″ icon=”tsuji.jpg” name=”TSUJI”]
TSUJI:やっと埼玉県と東京都に年間通したリーグ戦ができたんですよね
埼玉県は4種リーグっていうのができてこれがブロック数が多くて
埼玉だけでも相当なチームがあるんですよ。
これを機にもっと全国でリーグ戦が普及すればいいなと思いますね。
スペインだと育成年代からリーグ1部、2部があるらしいので
それが日本にもジュニア版のJ1、J2みたく普及すればいいんじゃないでしょうか。
[/speech_bubble]

By: UNICEF Ukraine
[speech_bubble type=”drop” subtype=”L1″ icon=”seiya.jpg” name=”SE”]
Seiya:でもスペインはお金ないクラブが多いから地域リーグどまりです
地域の中で1部、2部、3部
全国リーグはやってないですね。
全国リーグやってるのはユース以上で
全国大会が中学生か高校生までないんですよ。
だから小学生はやってないです。
スペイン人は小学生の全国のトーナメントに懐疑的ですよ。
育成の目的は勝ちじゃないのでやる必要あるの?って感じですね。
[/speech_bubble]
[speech_bubble type=”drop” subtype=”R1″ icon=”tsuji.jpg” name=”TSUJI”]
TSUJI:たしかに18歳までにトーナメントやると燃え尽き症候群になりやすいらしく
18歳以降の年齢になると選手登録の数がガクッと下がるみたいですからね。
それにプロに入ってからはリーグ戦が主体となりますし、
カップ戦は数えるほどしか試合がない。
あとJリーグのナビスコ(現在はルヴァン)や天皇杯もカップ戦の権威を保つためにベストメンバー規定を作っていますが
それをするならU-25のような育成の大会にすればいいと思います。
[/speech_bubble]
[speech_bubble type=”drop” subtype=”L1″ icon=”naoki.jpg” name=”NA”] NA:本日もありがとうございました。[/speech_bubble]
[speech_bubble type=”drop” subtype=”R1″ icon=”tsuji.jpg” name=”TSUJI”]
TSUJI:ありがとうございました。
[/speech_bubble]
もう一度ドーハの悲劇が起きないと日本サッカーの教育は根本から変わらないのかもしれない
子供がミスをし怒鳴るコーチをみた
あるイングランド人は自分の著書の中で
「日本にもし生まれてたら24歳までサッカーはできなかった」
と語っている。
この動画にでてくる指導者のような人を肯定する人も日本では少なくない。
特に50歳以上の人たちに多いといえる。
体罰方式の教育がいまだに浸透しているのも
体育という科目自体が軍隊訓練から派生したものとなれば当然といえよう。
サッカーもこの指導で強くなればいいのだが現実はそうはいかず
逆に才能ある子供の成長を阻んでいるとさえ思える。
体罰とネットで検索すれば無数の記事がでてくるのが今の日本。
今日取材した辻本さんのような子供に寄り添った指導者はまだまだ少ないと感じる。
ドイツはEUROの敗退から多くを学びサッカーの教育を14年かけて変えた
2014年のワールドカップで優勝したドイツはかつてどん底だった時代があり
それが2000年のEUROでのグループリーグ敗退の直後から始まっている。
ここからドイツは子供のサッカー教育から見直し、
14年後にワールドカップ優勝を成し遂げているのだ。
メンバーの中心選手はその改革によって生み出された才能ある者たちだった。
私にとって一番大事なのは人間関係を大切にすること。選手がどのように考えているかに気を配り、正しい方向へ導いていく。
ドイツサッカー連盟(DFB)UEFA・S級ライセンス主任指導教官フランク・ボルムートは
子供と向き合う上で大事なことは選手の考えということを主張している。
つまり優先すべきは指導者ではないということだ。
さらにボルムートは
ある程度の年齢までは勝ち点なしのリーグ戦を導入するなど、外からのプレッシャーを緩和したい。そうすればもっと多くのタレントを育て上げることができると、私は確信しているんだ
あくまでも勝負にこだわらない教育をすることがビッグスターを多く生むのに必要だと言っている。
勝ち点なしのリーグ戦など応援しているほうはつまらないが、重要なのは僕ら大人ではなく
子供にサッカーを好きになってもらうことなのだ。
勘違いしてはいけない。
ドイツでアンダー世代の指導経験のある
中野吉之伴さんが書いた
「ドイツの子供は審判なしでサッカーをする」
には日本では考えられないようなドイツのサッカー教育事情が
事細かに紹介されている。
 |
|
ドイツの子どもは審判なしでサッカーをする 自主性・向上心・思いやりを育み、子どもが伸びるメソッド 新品価格 |
![]()
事例の1つにあるがドイツでは自分の判断で練習を休むというから驚きだ。
日本でそんなことは許されないだろう。
もし仮に子供が自主的に休めばひどいコーチだと丸刈りにし足げりをくらわせるかもしれない。
日本はワールドカップに出場することが当たり前になっても根本的な教育は変わってないように思える。
ドイツは2000年のユーロの悲劇を教訓とし教育改革を実践してきた。
日本ももう一度1からサッカーを見つめ直すために
ワールドカップ出場を逃したかつてのドーハの悲劇のような
大事件を繰り返す必要があるかもしれない。
このくらいのことがないと大きく変わろうとは思わないのではないだろうか。
2050年までに自国開催でのワールドカップ優勝を目標に掲げる日本。
選手がヨーロッパのビッグクラブでプレーするだけで
それが達成できるほど甘いものではないことは
ドイツの例をみていればわかる。
日本の若い選手は早くに海外に行ったほうがいいと言われるが
子供にサッカーを教える指導者もカテゴリーに関係なく
今すぐに海外に行って学ぶべきではないだろうか。
今回取材させてもらったエボルテサッカースクールのホームページはこちら↓

小人数制のサッカースクールです。
子供さん一人一人に合わせた指導カリキュラムを作ってくれるので安心ですよ。
エボルテサッカースクールはこんな方におすすめ☆
- 個別で指導してもらいたい
- 思考力・判断力を伸ばしたい
- 自分の弱点・課題を明確にしたい
- メンタル面のサポートもほしい

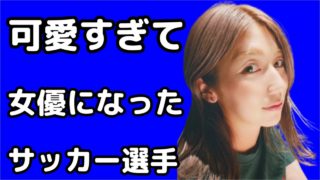

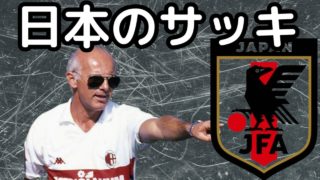


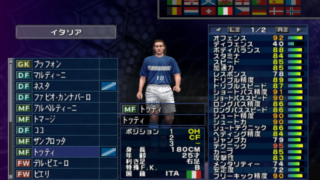





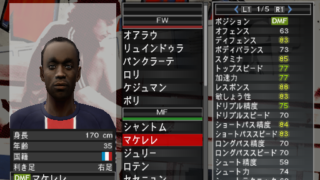






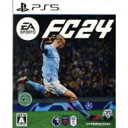
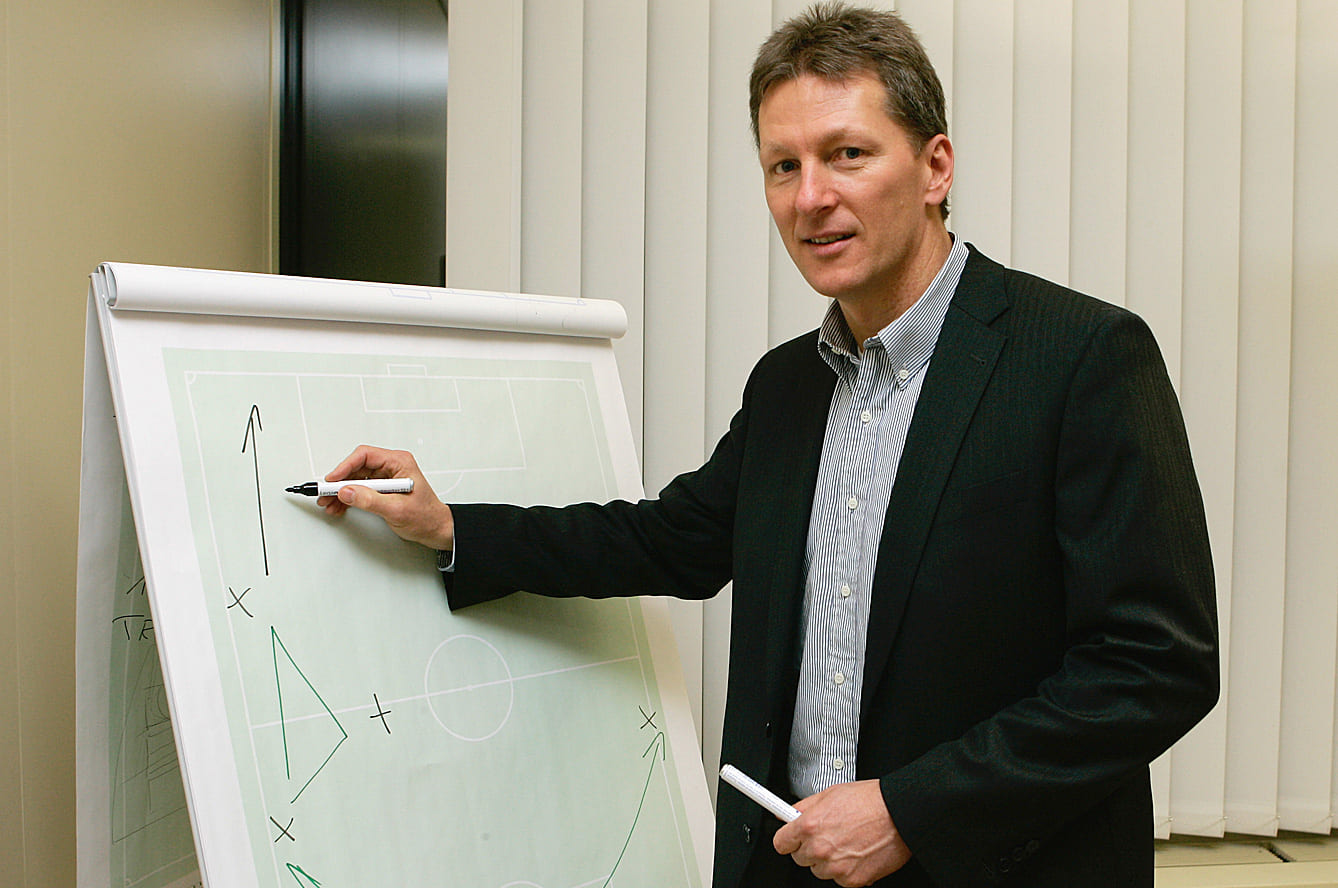

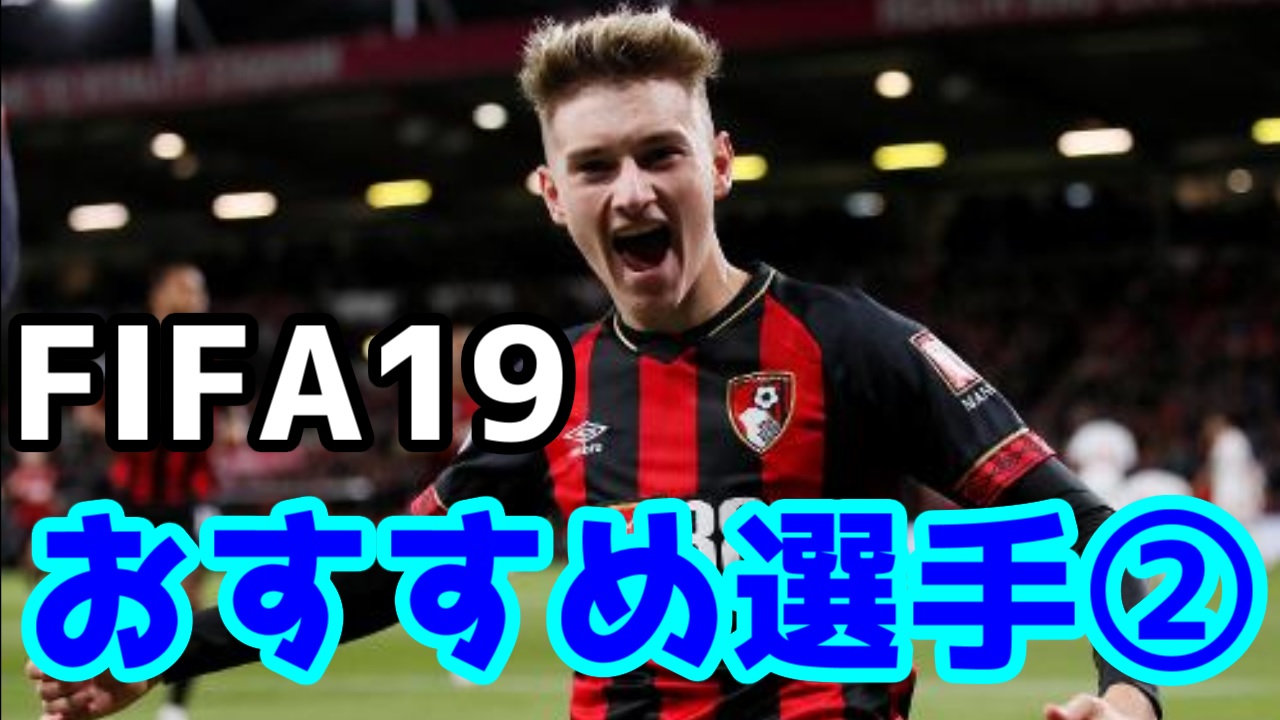
コメント